
臨床研修ブログ
水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。
医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。
患者さんはホントのことを言わない・・・解釈モデル
初期研修中に外来研修が必須となっているのをご存じでしょうか?多くの病院では地域研修などの際に1か月まとめて外来研修をするパターンが多いのですが、水戸済生会では当初から1年間をとおして外来を行う並行研修方式を取り入れています。
そんな研修医外来で実際にあったエピソードからです。
70才台の女性が受診しました。主訴は右肩の疼痛。でも、右上肢の可動制限や筋症状、神経症状も無く、よくよく聞けば、じつはすでに整形外科を受診して治療も開始されていました。
研修医が一通り話を聞き終えてから、隣で外来をやっている指導医のところに相談に来ました。「特に問題なさそうで、整形外科でも痛み止めを処方されています。何もすることもないと思うんですけど・・・、どうやって帰したらいいでしょう?」
確かに肩の痛みは心配な病気ではなさそうです。でも、こんな時あなたならどうしますか?考えてみてください。
↓
↓
↓
この時、指導医は「何かほかに受診した理由があるはずだから、もっと家庭の状況とか、最近の状況とかを聞き出してごらん」とアドバイスしました。
研修医がもう一度話を聞き出したところ・・・・、
・患者さんの知人が最近ガンで亡くなった。
・その知人が元気な時に、「肩が痛い」と言っていたので、自分も心配になってしまった。
・整形外科では痛み止めで治ると言われたけど、今のところあまり変わりない。
・もしかしたら内臓の病気?ガンかもしれないと思って内科を受診した。
ということが分かりました。
このような「肩の痛み→ガンかもしれない」は患者さんの「解釈モデル」と言いますが、ここで大事なことは、「患者さんの言葉を(そのまま)信じてはいけない」ということです。
どういう事かと言うと、患者さんからすれば病院を受診するのは、なんだかんだ言ってもハードルが高いものです。ドクターや看護師に「そんなことで受診するなんて」と言われたらどうしようと、ちょっとビクビクしながら受診しているのです。ですから、初めからホントのことを言ってくれません。何となくもっともらしい「建前」の理由を話すのです。
患者さんが話していることは基本的に建て前。
患者さんは(最初から)ホントのことを言わない。
患者さんの言葉を(そのまま)信じてはいけない。
話をしながら患者さんの「解釈モデル」を把握する必要がある。
このことが理解できると、あなたは患者さんから格段に良い情報(本音)を聞き出せるようになります。その本音の部分、つまり解釈モデルを理解して、不安や疑問を解決してあげることが大事です。ぜひこれから患者さんの話を聞く時は、これを意識してみてください。
(編集長)

朝の回診風景
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?
どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
https://recruit-mito-saisei.jp/entry
済生会学会2025 in 松山
済生会は全国に病院や福祉施設がたくさんありますが、臨床研修病院だけでも34病院あります。
そんな済生会では年に1回、総裁である秋篠宮殿下も出席して済生会学会が開催されています。コロナの影響で中断したものの、2年前から再開されて昨年は熊本、今年は愛媛の松山での開催となりました。
この済生会学会にあわせて、全国の済生会病院で初期研修をしている1年目の研修医を対象とした合同
セミナーが開催されます。済生会全体となると初期研修医1年目だけで約260名にもなりますが、今年も編集長と当院のJ1全員で参加してきました。

済生会は、現在の初期研修制度が始まった当初から卒後7年目以上の医師を対象とした指導医講習会を精力的に開催して研修医教育に力を入れてきました。また、多くの病院で医学部の学生実習を受け入れています。
初期研修1年目がもうすぐ終わり後輩たちを迎えることや、医学生の実習に関わる立場になるという背景もあって、数年前からこの合同セミナーでは「教わる側から教える側へ」というテーマで構成しています。前半では「理想の医師像」、後半では「より良い研修を行うためには」というお題目でのグループディスカッションで、各病院の違いなどを互いに把握しながらの議論が盛り上がっていました。
今年のディスカッションで編集長的に驚いたことは、後輩や医学生に教えるにあたってコミュニケーションをとる重要性を各グループで指摘していたことと、そのコミュニケーションをするために「飲みに行く」というワードがいくつものグループで出されていたことです。
昨年はこのような「飲み会」というワードをほとんど見かけることはなかったと記憶しているのですが、ちょうどコロナで飲み会などがなかった世代なので「飲み会」が復活してきたことに驚かされました。
ちなみにこの場でのプロダクトは回収されて、毎年データとして蓄積されています。指導医側からすると、ハッとさせられる視点があり、研修医だけでなく指導医にとっても大事なイベントになっています。
もちろん終了後は研修医らと愛媛のおいしいものをいただいて帰りました♪
(編集長)

グループディスカッションの一コマ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?
どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
https://recruit-mito-saisei.jp/entry
病院見学のススメ
毎日寒い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか?今冬は各地で大雪の影響が出ていますね。水戸では雪の影響はないのですが、寒さのためなのか偕楽園の梅はまだ咲き始めていません。
4年生や5年生のあなたは春休み中の遊びの予定を考えていると思いますが、春休みが終わるとあっという間にマッチング面接の時期になってしまいますから、病院見学の予定もぜひ考えてください。
時間や予算の制約があるかもしれませんが、マッチングは自分の「研修先」を決めるものですが、言い方を変えると「就職先」を決めることです。ですから、それなりの時間と労力を費やすことは必要だと思います。
このブログでは何度も紹介しているネタではありますが、今回は病院見学のポイントを紹介します。
・可能な限り、病院見学に行きましょう。
レジナビなどのサイトやWeb病院説明会、リアルイベントで情報収集をするのが当たり前になりましたが、それだけでは不十分だと思います。実際に行ってみると、それぞれの病院によって想像以上に雰囲気が違うことに気づくはずです。行けない時には、Web病院説明会で質問コーナーや個別面談のようなコーナーを設けているものが増えているので、積極的に利用して雰囲気をつかむのが良いと思います。
・病院見学に行った際のポイントは・・・、
指導医クラスの話は、半分程度に聞いておけばOKです。なぜかと言えば、基本的にイイことしか言わないからです(編集長にも自覚があります・・・)。
・必ず研修医たちに直接話を聞きましょう。
研修医の先生たちにあなたの知りたいことを質問してみましょう。研修医も1年前には同じように悩んでいた訳ですから、たとえあなたがつまらない質問かもと思っても、そのような質問こそ聞いておくべきです。一番参考になる答えが返ってくるはずです。
そして研修医たちの元気の良さや看護師さんや技師さんたちの雰囲気にも注目してみて下さい。研修医を育ててくれるのは指導医だけではありませんからね。
・気になった病院には2回、3回と見学に行きましょう。
何故かと言えば、どうしても初めてのところは緊張するし、余裕がないので周りを見ているようで見えていません。2回目になると余裕ができて、おなじ病院見学でも見える風景が違うはずです。
加えて1回目にあった研修医が、2回目にはものすごく頼りになる研修医に見えるはず。この時期なら、1年目でもかなり仕事ができるようになっていますので、そんな研修医の姿を見ると、あなたの研修のイメージも描きやすくなるはずです。
当院に病院見学に来ていただいた方からは
・研修医の先生方のモチベーションがとても高く、見習いたいと思いました。
・小児科では、済生会での研修だけでなくこども病院にも行くことができて、初期研修後のイメージも持つことができました。
・昼食の時に研修医の先生とお話する時間が確保されていて、聞きたいことを全部聞くことができ、とても参考になった。
・研修医の先生方とたくさんお話を伺うことができました。またとても気さくにお話をさせていただきました。
・研修医の先生方が主体的に診療に関わっているのを見ることができました。
といったコメントをいただいています。
そろそろ春休みの病院見学の申し込みをいただいています。あなたもお早めに下のリンクからお申し込みください!
↓
(編集長)

吸入指導のレクチャーでの一コマ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆応募いただき有難うございました!
第23回水戸医学生セミナーは定員に達したので
応募を締め切らせていただきました。
現在メディカルラリーの準備中です。
合格祈願2025
いよいよ医師国家試験も今週末となりましたが、いかがお過ごしでしょうか?
今まで何度も試験を受けてきたはずですが、どうしても試験前というのは不安や焦りを感じてしまうものです。国試となればなおさらです。
でも、国試は医師になるための通過点ですから、医学部を目指した時の気持ちをもう一度思い出して、そしてこれまでコツコツと続けてきた勉強量を信じて、さらに4月から患者さんの前に立っている自分をイメージして、自信をもって臨んでほしいと思います。
お天気は寒波の影響で、特に日本海側では大雪が予想されています。十分わかっていると思いますが、会場までの時間や寒さ対策など、普段以上に余裕をもって行動してください。
体調を崩さぬように最後まで気を抜かず、国試当日も最後まで頑張って、合格を手にしてください!当院スタッフ一同、あなたの合格を心よりお祈りしています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆第23回水戸医学生セミナー
~復活!メディカルラリーで救急のエッセンスを体験しよう~
2025年3月15日(土)、16日(日)に開催します。
定員まで残り1名となりました!
JATEC,MCLSなどの内容を盛り込んだメディカルラリーに挑戦してください!
【御礼】レジナビにご参加いただき有難うございました!
1月28日に「レジナビFairオンライン2025 東日本Week ~臨床研修プログラム~」に登壇しました。
マッチングが一段落してホッとしていたのですが、もう春休みに向けてのレジナビでした。うれしいことに年々医学生の参加者が増加していて、この時期としては我々の予想を超える50名以上の医学生にご参加いただきました。どうも有難うございました!
ご承知の通り、研修病院探しではレジナビは完全に定番となっています。20分という短い時間ですが、司会がいて上手に進行してくれるので、沈黙する時間がなく、我々もとてもやりやすいのが特徴です。
いつも通り前半は病院説明、後半の質疑応答ではJ1の土田先生と蛯子先生の2人が加わってくれました。J1と言っても、この時期の二人はそれなりに場数を踏んでたくましくなっていますので、質問に対して、現場目線の良い回答をしてくれていました。
普段から言っていることなのですが、今回のレジナビのようなWebでの情報収集をして、必ず病院見学に足を運んで下さい。Webではわからない病院ごとの雰囲気の違いに気づくはずです。そして病院見学では指導医からの話は半分程度に聞いておき、研修医から直接話を聞くのが大事なポイントです。
すぐに春休みの記事になりますので、水戸済生会にも病院見学にお越しください。見学を希望される方は下記のリンクからお申し込みください! お待ちしています!!
もう一つ、3月15日、16日に開催予定の「第23回水戸医学生セミナー」が定員まであと僅かになりました。参加を考えているあなたは、ページ最下段のリンクから今すぐお申し込みください!
(編集長)

今回はこの二人♪
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆第23回水戸医学生セミナー
~復活!メディカルラリーで救急のエッセンスを体験しよう~
2025年3月15日(土)、16日(日)に開催します。
定員まで残り2名です!
JATEC,MCLSなどの内容を盛り込んだメディカルラリーに挑戦してください!
基本的臨床能力評価試験2025
毎年この時期は当院の研修医らのテストの季節です。
テストと言っても、初期研修医の客観的な臨床能力の実力を知るためのテストで、日本医療教育プログラム推進機構(JAMEP)というNPOが行っている基本的臨床能力評価試験(GM-ITE)というものです。
CBT方式で研修医部屋の自分の机で受験するうえ、夜勤や夜勤明けの研修医が必ずいるので全員そろうこともなく、あまりテストという雰囲気を感じさせないのですが、もちろん真剣に臨んでいました。
試験の内容は、基本的臨床能力と言っても幅広い分野から出題され、総合診療をやっている病院には有利な印象を受けましたが、毎日の臨床で経験したことをこまめに振り返っておけば、そこそこできる問題だと思います。英文の問題もボリュームがあって、早く終わる人はおらず、全員が試験時間が終わるまで取り組んでいました。
初期研修中はホントに自分は実力がついているのか?と不安になることがあります。自分の実力を知る方法としては、他の研修病院に行った同期の研修医と会話するとか、合同セミナーのような時のちょっとした発言などから、「スゲーやつかも」とか、「自分の方が結構できてるかも」と勝手に判断するくらいしかありませんでした。でも、このテストを受ければ自分の実力が全国でどのあたりなのかが分かるので、とても良い機会だと思っています。
受験者の母集団が優秀ですから、テストを甘く考えていると信じられないような低い偏差値になることがあります(笑)。でもJ1よりJ2の方が成績が良くなっていますから、成長しているのが数字にも表れていますので安心しています。さて、今年の成績がどうなってういるのか編集長的にはすごく楽しみです♪
(編集長)

テスト中の一コマ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆第23回水戸医学生セミナー
~復活!メディカルラリーで救急のエッセンスを体験しよう~
2025年3月15日(土)、16日(日)に開催します。
JATEC,MCLSなどの内容を盛り込んだメディカルラリーに挑戦してください!
国試前の過ごし方
年が明けて、国家試験まで1か月を切りました。
受験するあなたも、トップギアに入っていると思います。日本海側は大雪のところが多いようですが、どうぞ体調管理に気を付けて過ごしてください。
さて、昨年もこの時期に先輩から国試前のあなたにアドバイスの記事を載せました。今回は当院J1のメッシ先生からの記事です。どうぞご覧ください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆第23回水戸医学生セミナー
~復活!メディカルラリーで救急のエッセンスを体験しよう~
2025年3月15日(土)、16日(日)に開催します。
JATEC,MCLSなどの内容を盛り込んだメディカルラリーに挑戦してください!
新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます!
本年もこのブログをどうぞよろしくお願い申し上げます。
新年を迎えて、あなたは今年の目標、そして将来の目標を考えてみましたか?6年生のあなたなら今年の目標はもちろん国試合格ですが、臨床研修が始まってからの将来の目標も忘れずに考えてくみてださい。
さて、その将来の目標に絡めての話ですが、内科系であっても外科系であっても、何か一つの仕事をマスターするには時間が必要ですよね。単に仕事ができるのではなく、想定されるあらゆる状況下できちんと結果を出せるようになるには、かなりの時間が必要なことはあなたも想像できると思いますが、どのくらいの時間を考えておけば良いのでしょうか?
そこで、今回はあなたに「1万時間の法則」を紹介したいと思います。
「1万時間の法則」とは、マルコム・グラッドウェルの著書『天才!成功する人々の法則』で紹介された、ある分野で一流になるためには1万時間の練習や努力が必要だという話です。1万時間と言えば、毎日3時間の練習を10年間続けることに相当します。
10年と言われるとガッカリする人もいると思いますが、ここで注意してほしいのは、この法則を「何かに熟達するには1万時間の練習が必要である」「1万時間練習しないと技能を身につけることはできない」という意味ではないということです。
ちょっと考えればわかることですが、練習時間だけが全てを決めるわけではありませんし、効率よく学べばもっと短い時間で熟達できるはずです。必ずしも1万時間を費やす必要はありません。
でも、何かに熟達するには自分から勉強して、繰り返し練習して、フィードバックを受けて、また繰り返すことが必要で、それには時間がかかるものなのです。手技の習得だとこのプロセスはイメージしやすいですが、手技以外の業務でも同じことが言えます。
すぐに上達しないから、自分にはセンスがない、自分には向いていないと判断するのは賢いとは言えません。
そして、時間をかけて熟達するにはいくつかコツがあります。よく言われることですが、目標を明確にする、そして努力の対象を好きになる、努力を習慣化することで、熟達するまでの長い期間でもモチベーションも維持できます。
1万時間の法則は、医学生のあなたにも、研修医や専攻医のあなたにとっても、大いに参考になる考え方だと思います。長い道のりを歩む中で、日々の努力を積み重ねることが成長への鍵となります。2025年も、皆さんが目標に向かって努力し続けることを応援しています。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
年末のご挨拶
早いもので、今日は大晦日となりました。北関東の年末年始の天気は崩れないようですが、日本海側は雪が多いようです。今夜から元旦にかけて寒さが一段厳しくなるそうですので、どうぞ体調管理には気を付けてお過ごしください。
さて、今年は元旦から能登半島で大きな地震があり、その数日後に飛行機の衝突事故というショッキングなニュースから始まった年でした。東日本大震災を経験した編集長としては、能登半島の地震は他人ごととは思えず、1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
さて、当院の研修医たちを見ると、J2は自分の進路は決まったことで、新たなモチベーションをもって働いてくれています。J1も仕事をうまくこなせるようになって、だいぶ自信がついた顔つきになってきて頼もしい限りです。
4月からは10名の後輩たちが来ますので、水戸済生会の先輩らしい姿を見せられるようになってもらいたいです。
6年生のあなたは、いよいよ国試に向けてラストスパートになります。今まで幾多の試験を乗り越えてきたので問題ないはずですが、試験は最後まで分かりませんから、体調管理に十分に注意を払って頑張ってください!
さて、この記事が年内は最後になります。しばらく数えていなかったのですが、気づいたらブログも開始当初から今回で1379回目でした。こうして継続できているのもあなたに読んでいただいているからです。新しい年を迎えてもあなたにとって価値ある情報をお届けできるよう努力して参りますので、当ブログを引き続きよろしくお願いいたします。
どうぞ良いお年をお迎えください。
(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
CPC開催報告
先週のことですが院内CPCを開催しました。
当院のCPCは、毎月開催されている水戸市医師会病棟検討会という地域の先生方にも参加いただく症例検討会の場を利用して開催していますが、昨年度からそれとは別枠で朝に開催するようになりました。
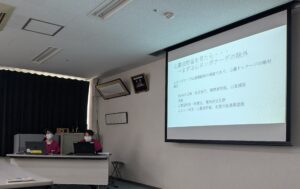
症例は80歳台女性で、心嚢液貯留で紹介された患者さんです。心嚢穿刺を行って、その細胞診からリンパ腫が疑われたのですが、急な経過で亡くなりました。
亡くなる前に行ったCTや心エコーではわからなかったリンパ腫の広がりが、病理解剖で明らかとなりました。また、直接の死因も解剖で明らかになるなど貴重な症例でした。
リンパ腫の分類にはいろいろあるのは知っていたものの、編集長的には知らないことばかりで、血液内科医と病理医で議論が白熱するCPCとなりました。
臨床側と病理側とで2名のJ2が関わりましたが、学びの多いCPCになったと思います。
(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓

