
臨床研修ブログ
- トップ
- 臨床研修ブログ
水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。
医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。
狭心症の診断にはホルター?
いきなりですが、あなたに質問です。
60歳台の男性が外来に来ました。他院で高血圧と糖尿病の治療を受けているそうです。数か月前から労作時に4~5分続く、胸やけのような胸部不快感を自覚するとのこと。聴診では過剰心音も心雑音もない。心電図と胸部レントゲンは正常でした。どうやら安定狭心症が疑わしい状況です。
では、安定狭心症の診断を進めるために、あなたならどんな検査をしますか?
↓
↓
↓
こんな質問をすると、約半数以上の研修医が心エコーとホルターと答えました。では狭心症の診断にホルターは有用なのでしょうか?
UpToDate(2024年12月時点)を見ると安定狭心症の診断には、画像を用いた負荷テスト(Stress test with imaging)として運動負荷心電図(Treadmill test)や運動または薬剤負荷心筋シンチ、負荷心エコー、負荷MRIが記載されています。
いずれも運動や薬剤負荷をかけることで虚血の有無と予後判定に役立つ情報が得られます。そのうえで 「冠動脈CTや冠動脈造影」 など解剖学的な評価に進みます。
そう、ホルターとは書いてないのです。
もう一つ研修医が答えてくれた心エコーは、UpToDateにも全員にやる検査として記載されています。ただ、冠動脈支配に一致した壁運動の低下といった典型的な所見が見られたらより精度が高くなりますが、それだけでは狭心症の診断はできません。つまり、安定狭心症の診断には何らの負荷をかける必要があるのです。
その疾患の診断にはどんな検査が必要なのか?その検査をすることで得られる情報は何なのか?
自分が担当している患者さんで指導医に言われた検査も、こういった点を整理しておくと応用が利くようになりますよ。
(編集長)

回診の一コマ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
【ご参加有難うございました!】エムスリーのオンライン病院座談会
12月17日にエムスリーのオンライン病院座談会に当院も参加しました。この時期としては多めの20名近くの方々にご参加いただきました。どうも有難うございました。
エムスリーの場合は司会者付きで40分枠という余裕のある形式です。このため前半のスライドを使った病院紹介もレジナビより内容を盛り込めますし、後半の質疑応答では司会者が上手にコントロールしてくれます。
今回のエムスリーのオンライン座談会は「専門研修で選ぶ!内科系特集」というテーマでしたので、編集長と内科専攻医2年目(卒後4年目)の高野先生とで臨みました。後半の質疑応答では、はじめのうちこそ質問が出ませんでしたが、徐々に質問が増えてきて大変嬉しかったです!
ただ、編集長的には前半の病院紹介は反省点がありました。というのも、想定では初期研修医も数名は参加しているかと考えて、内科専門プログラムの説明に寄せていたのですが、実際の参加者は5年生が最多で、4年生、3年生もいました。であれば、もっと初期研修のことも触れる内容にしておけばよかったと反省しています。質問も初期研修に絡めてのことが多かったので、次の機会には修正していきます!
司会者も話していたのですが、ぜひオンライン説明会などで情報収集をして、実際に病院見学に足を運んでください。行ってみることで、実際の雰囲気が分かりますし、病院ごとにだいぶ違うことも分かるはずです。
現在冬休み中の病院見学を受け付けています。まだ空いている日もありますので、ぜひ下記リンクからお問い合わせください♪
(編集長)
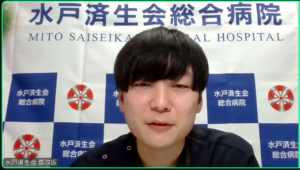
質問に答えている高野先生
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
「まあいいか」はNGワード
あなたはERやベッドサイド、手術室、内視鏡室、カテ室などで患者さんの採血をしたり、CVやPICCを入れたり、縫合したり、穿刺やカテ操作など、色々な処置をしますよね。
意識がない患者さんや全身麻酔の時もありますが、局所麻酔のみで意識のある患者さんへの処置も多くあります。
あなたが2年目以上の研修医なら自分でやっている時に限らず、後輩の研修医がやるのを指導する時もあるかもしれません。
そんな時に、つい「まあいいか」と口にしていないでしょうか?
「まあいいか」の背後には、意識していなくとも自分としては完璧じゃない、もっと上手くできたはずとか、もっときれいにできたはず、もっと速くできたはずなど、色々な反省の気持ちがあって出てくる言葉ではないでしょうか。
でも、これを聞いた患者さんや家族はどう思うでしょう?
・イマイチの出来だけど、まあいいかで終わらせたってこと?
・何か失敗したけど、ごまかせるレベルだからイイってこと?
・まじめにやってくれてないの?
などと、否定的に受け止めてしまうのではないでしょうか?
患者さんや家族は、頑張っても結果がダメな時があるのは分かってくれています。でも、手を抜いたり、まじめに取り組まないで、ダメな結果になったら許してくれません。
「まあいいか」は、そんな時にネガティブな印象を与えてしまう言葉の一つだと思います。つい口から出てしまわないように気をつけてみてください。
(編集長)

完璧を目指しています♪
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
ステロイド外用薬のポイント
昨日は8月、10月に引き続き、水戸協同病院皮膚科の田口先生にお越しいただいて皮膚科教育レクチャーを開催しました。今回は外用薬のポイント、疥癬、壊死性筋膜炎ともりだくさんの内容でした。
その中からステロイド外用薬のポイントをシェアします。
そもそもステロイド外用薬は、湿疹、皮膚炎、かぶれ、虫さされに用いられるものですが、これらは遭遇する頻度が非常に多いため、湿疹を疑ったらステロイドの使用を恐れることは無いそうです。
ステロイド外用薬の使い方としては、
顔首・陰部は弱く、足底・手掌は最強で、その他は中間
具体的には、
・顔・首・陰部ならMediumクラスのステロイド(例:アルメタ、ロコイド、キンダベート)
・手掌・足底ならStrongest クラスのステロイド(例:デルモベート)
・その他の部位ならStrong以上でOK(例:ネリゾナ、メサデルム、リンデロンVG)
とすれば良いそうです。これなら覚えられますね。
繰り返しになりますが、湿疹を疑ったらステロイド外用を使ってOKですが、
・1か月で良くならなかったら一度立ち止まる
ステロイドの局所副作用の可能性やステロイドの効かない疾患を考える必要があります。
・4つの「カ」を思い出す
4つの「カ」とはステロイド外用の効かない、①カポジ水痘様発疹症、②疥癬(かいせん)、③カビ、④Carinoma in situのこと。これらの可能性がないかを考えて、皮膚科専門医に相談しましょう。
(編集長)

実際に軟膏、クリーム、ローションの
使い心地を確認
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
「できない」を「できる」に変える方法
例えば、あなたがCVやPICCを入れるとき、またはERで挿管するとき、指導医からやり方を教えてもらったり、すでに経験済の同期から教えてもらったり、シュミレーターやYouTube動画で勉強してから臨みますよね。もちろん初めから上手くできる人はいませんが、何度か失敗すると「自分には向いていない」「できない」と思ってしまい、ついついやらなくなりませんか?せっかく指導医から「やってみる?」と言われても、些細な理由をつけてチャンスを同期に譲ったり・・・。
我々の脳は一度「できない」と思うと、「できない」記憶の連鎖がループのように回り始め、なかなかそこから抜け出せなるクセがあるそうです。それをそのままにしておくと、ホントに「できない自分」が作られてしまいます。今回はそんな「できない」から「できる」に変える方法を紹介します。
1.「できなかった」記憶を「できた」記憶に変える
失敗の記憶は、少し見方をズラしてあげると「できた」記憶に変えることができます。たとえば、過去の失敗から「できた」を探すことで記憶をポジティブなものに変えることができます。
例えば、エコーガイドでPICCの挿入を例にすると、「PICCを挿入できなかった」という失敗があったとして、その記憶をあらためて見直して「できた」ところを振り返ってみましょう。
例えば
・患者さんの体位はよかった
・エコーで目的の血管はきれいに描出できていた
・患者さんに上手く声掛けできていた
など、いろいろ出てくると思います。我々は何か失敗して、不快な感情、恥ずかしかったという感情がわくと、「全然ダメだった…」と一般化してしまうクセがあります。でも、100%ダメってことはまずありません。些細なことでOKなので、「できた」と思えることを1つずつ思い出してみると、「できなかった」が「できた」という記憶に変わってきます。
2.「何ができていないか」を具体化する
これとは逆に「何ができていないか」をできるだけ具体化していく作業も重要です。前述のとおり「全然できなかった」と一般化して認識してしまいがちですが、これではどう改善したらいいかわからないから「できなかった」という自分が強化されるだけです。なので、「何ができていなかったか」を具体的にすることが重要です。
先ほどのPICC挿入での失敗を分析してみると
・左手で持っていたエコーが動いてしまい、針先を見失った。
・消毒前にエコーで確認した時の体位と消毒して覆布をかけた時の体位が少し変わってしまい、見えにくくなった。
・穿刺は上手くいったけど、左手で持っていた外套を動かしてしまった。
ということが出てくるかもしれません。何ができたのか?何ができなかったのか?を具体的に分けることで次の改善案やアクションが生まれて、「できた」「乗り越えた」という記憶に変えることができます。
ただし、できなかった記憶と向き合うことは辛いので、みんなやりたがりません。でも、みんなやらないからこそ、これをやることで大きな差がつきます。プロフェッショナルは、「できなかった」体験と向き合うプロでもあります。ぜひ失敗と向き合って、「できる」を少しずつ増やしてみてください。
(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
職業歴の効用
あなたは問診の際に患者さんの職業(もしくは職業歴)を聞いていますか?
編集長が学生の時は、職業を患者さんに聞くのは、なんだか職務質問をしているみたいで、患者さんを不愉快にさせてしまうのではないか・・・、と当時はその必要性を全く理解できませんでした。ところが今は外来でもERでも、ほぼ全例で患者さんの職業を聞いています。
なぜかと言うと、3つの点でメリットがあると思っているからです。
1つ目は、診断に役に立ちます。
職業や家族構成、宗教、嗜好品や趣味などを聞くのは、診断の大きなヒントになるのは間違いありません。例えば農業や林業を仕事にしている人ならツツガムシを鑑別に挙げるとか、家族内発症があるとか、HTLV1とか住血吸虫とかなら、出身地がどこかが大きなヒントになります。
2つ目は、治療に役立ちます。
内服薬のアドヒアランスを上げるために職業を把握するのは重要です。例えば飲食店(居酒屋)をやっている人に糖尿病薬を処方するとします。居酒屋なら、起床は10時ごろで朝食は取らずに昼頃から仕込みをして、開店前に食事。夕食は店を閉めて片付けが終わった0時過ぎという感じ。こんな仕事をしている患者さんに糖尿病薬を朝食後として処方してもいつ飲めばいいのか分かりません。患者さんの生活スタイルに合わせて処方時間を変えるなど、アドヒアランスを上げる工夫が大事ですが、職業歴は大きなヒントをくれます。
3つ目は、コミュニケーションを円滑にする重要なツールだからです。
例えば、金融関係や経理をやっている患者さんなら、具体的に何%とか数字を示して他の疾患との比較をすると理解してくれることがあります。また編集長の経験した患者さんの中には、研究機関に勤めている人で根拠となる文献を渡したことがありました。
一方で、農家のおじさんに同じように説明をしても、さっぱり理解してくれませんでした。数字をあまり入れずに、分かりやすい例えを用いる工夫がいります。
このように、ERやベッドサイドであなたが患者さんと話している時、実はあなたの言葉が患者さんに理解できない言葉になっていることが良くあります。良く理解できていなくても「はい」と返事しているのです。
コミュニケーションの場においては、常に相手の立場、相手の考え方、相手の気持ちを考える必要があります。職業を把握することは、患者さんを理解する重要なヒントをくれます。そして患者さんが理解しやすいように説明の仕方を変えることが出来ます。あなたも上手にコミュニケーションがとれるように、ぜひ職業を必ず聞いてみてください。
(編集長)

総合内科の夕カンファ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
その心筋梗塞はヤバイのか?
あなたは担当患者さんの既往歴に「心筋梗塞」とか「STEMI」とあったら、それ以上の情報を取りに行っていますか?
もしあなたが循環器内科のローテーションを終えているのなら経験しているかもしれませんが、STEMIといってもPCI後は何事もなく、すぐに退院してその後も入院前と変わりなく生活している人も多くいます。一方で、なかなか退院できなかったり、退院しても心不全などで何度も入院を繰り返す人もいます。さらに元気に過ごしている患者さんの中でも、EFが正常な人もいれば、EFが30~40%と低下している人もいます。
あなたの担当患者さんがこれから化学療法を予定しているなら、レジメの中には心機能に影響するため避けなければいけないレジメもあります。これから手術を受ける患者さんなら、周術期の管理や輸液に注意しなければいけない患者さんもいます。
でも、上述のように心筋梗塞の既往がある患者さんの中でも、ヤバイ患者さんから、ほぼ心配しなくて良い患者さんまで幅広くいるので、心筋梗塞の既往があるだけでレジメが使えないとか、手術ができないと判断するのは良いことではないと思います。
それよりも心筋梗塞の既往がある患者さんの中から「ヤバイ心筋梗塞」の患者さんを、あなたが見つけ出せるようにしておくことが重要です。
では、心筋梗塞の既往がある患者さんのなかで、どこを見れば「ヤバイ心筋梗塞」を見つけ出せるでしょうか?あなたは考えてみたことがありますか?
編集長は心筋梗塞の既往を見つけたら、カルテを遡って以下の項目をチェックしているので参考にしてみて下さい。
・EF
循環器が苦手な人でも知っているのがEFです。循環器内科医にとってはEFが低いだけで恐れることはないのですが、そうは言ってもEFが低い人は注意が必要です。
・発症時の最大CPK
心筋梗塞発症時の最大CPKが分かればチェックしておきます。このCPKは梗塞量(=心筋ダメージ)を反映するので、高いほどヤバイ心筋梗塞と言えます。ザックリですが、CPKが6000以上ならダメージは大きいと思ってOKです。8000以上、特に10000以上なら循環器内科医でも相当にヤバイと考えて慎重に見ているはずです。
・残存病変の有無
心筋梗塞を起こした部位(責任病変)以外に狭窄病変があれば要注意です。
・合併症の有無
心筋梗塞発症直後やPCI中の心室頻拍(VT)や心室細動(Vf)は急性虚血によるものなので、その後はあまり心配いりません。ところが発症から1週間以上経過してからのVTやVfは植え込み型除細動器(ICD)が必要になり要注意です。また、重篤な機械的合併症(乳頭筋不全、心室中隔穿孔、左室自由壁破裂)はそれだけ心筋ダメージが大きいことを意味しますのでヤバイ心筋梗塞です。また心筋梗塞後に心不全を来したのであれば、これだけでヤバイ心筋梗塞と思ってください。
あなたもこれらの情報をカルテから探して、ヤバイ心筋梗塞を見つけ出せるようになってください。
(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
令和7年度採用予定者の内定式
先日のことですが、当院にマッチした10名を迎えてZoomでの内定式を開催しました。
内定式には内定者10名とJ1,J2の先輩たち、さらに院長と編集長、Nao先生も参加しました。内定者たちにとっては同期となる仲間同士の初顔合わせでした。
J1から歓迎のメッセージ、院長からの歓迎のあいさつと内定者全員の自己紹介と続き、編集長のあいさつで中締めとなりました。
ここで院長と編集長のおじさん二人は退場して、Nao先生の司会で内定者らの素朴な質問にJ1,J2らが回答するなどして、だいぶリラックスした雰囲気で終わったようです。
じつは今回の内定者10名のうち、女性が8名という今までにないメンバー構成となっています。当院の先輩たちにはいろいろな人がいたので、少々のことでは驚かない編集長ですが、今回のマッチング結果には驚かされました。さらに出身地も様々で、年齢層も幅広く、いろいろな意味で刺激しあえる学年になることを期待しています。
当院の内定者に限らず、6年生のあなたは国試に合格しないことには話が始まりません。国試までの時間は短くなってきましたので、体調に気を付けながら最後まで頑張ってください!
(編集長)

内定式の一コマ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
喘息の診断は?・・・井上先生の呼吸器レクチャーより
「喘息って、どうやって診断するの?」
研修医に質問すると、ほぼ全員が無言になります。
喘息の治療のことは覚えていても、診断となると自信をもって答える研修医はごくわずか。
それもそのはずです。
喘息の定義を確認してみると、「気道の慢性炎症を本態とし、変動性を持った気道狭窄による喘鳴、呼吸困難、胸苦しさや咳などの臨床症状で特徴づけられる多様性を有する疾患」とフワッとしたものになっていて、例えば、COPDのように「1秒率が70%未満」など、数値では定義されないのが喘息の難しいところだと言えます。
先日のことですが、そんな喘息に関して山形大学呼吸器内科の井上先生にレクチャーしていただきました。
喘息の特徴をまとめておくと、
・喘息は小児から高齢者まですべての年代において発症し得る疾患
・喘息の診断には臨床症状がより重要であるため、詳細な問診が必要
・喘息の診断には「ゴールデンスタンダード」となりうる客観的指標はない
・症状の中で最も特異性の高い症状が「喘鳴」、最も頻度が多いのが「咳嗽」
・喘息を疑う症状(喘鳴、咳嗽、喀痰、胸苦しさ、息苦しさ、胸痛)がある場合には下の問診チェックリストに従って問診を行う
喘息と診断するには問診が重要なのですが、見落としを防ぐために以下の問診チェックリストを利用してください。
<問診チェックリスト>
大項目
喘息を疑う症状(喘鳴、咳嗽、喀痰、胸苦しさ、息苦しさ、胸痛)がある
小項目
〔症状〕
①ステロイドを含む吸入薬もしくは経口ステロイド薬で呼吸器症状が改善したことがある
②喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)を感じたことがある
③3週間以上持続する咳嗽を経験したことがある
④夜間を中心とした咳嗽を経験したことがある
⑤息苦しい感じを伴う咳嗽を経験したことがある
⑥症状は日内変動がある
⑦症状は季節性に変化する
⑧症状は香水や選考などの香りで誘発される
⑨冷気によって呼吸器症状が誘発される
〔背景〕
⑩喘息を指摘されたことがある(小児喘息も含む)
⑪両親もしくは兄弟に喘息がいる
⑫好酸球性副鼻腔炎がある
⑬アレルギー性鼻炎がある
⑭ペットを飼い始めて1年以内である
⑮末梢血好酸球が300/μl以上
⑯アレルギー検査(血液もしくは皮膚検査)にてダニ、真菌、動物に陽性を示す
「大項目+小項目のうちいずれか1つ以上」あれば喘息を疑います。
(喘息診療実践ガイドライン2024)
繰り返しになりますが、喘息の診断は問診から疑っていくことが重要です。あなたもチェックリストを使いながら、喘息を診断できるようになって下さい。
(編集長)

背景は山形の銀山温泉♪
いいところですよ!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
HIVで知っておくべきこと(5)・・・松永先生レクチャーより
前回まで症例ベースでHIVを疑う状況を紹介してきました。
当院でHIVに遭遇する機会は稀かもしれませんが、病歴や身体所見などから違和感を感じてHIVを鑑別に入れておくことは必要です。今までのポイントをまとめると、
<HIVに出会う時>
【急性期】
インフルエンザ様、伝染性単核球症様、無菌性髄膜炎、皮疹
【無症候期】
性感染症(肝炎、赤痢アメーバ含む)、繰り返す帯状疱疹、口腔カンジダ、脂漏性皮膚炎、結核
【AIDS発症期】
ニューモシスチス肺炎、クリプトコッカス髄膜炎、各種のAIDS指標疾患
<身体診察で重要な点>
・診ようとする人には見える
・毎日、繰り返して行う
・眼、皮膚、リンパ節、心音、腹部などに特に注意
–原因不明の皮疹、リンパ節腫大、肝腫大⇒生検対象
・いつも診ないところを診る
–「孔の周り」に注意せよ→「眼、耳、鼻、口、肛門」
松永先生のレクチャーでは他にもHIVに関する内容が盛りだくさんでしたが、以下のポイントのみ紹介しておきます。あなたもHIV患者さんに遭遇した時に焦ることがないようにしておきましょう。
・HIV感染症は長期生存可能な疾患である
・良好にコントロールされているHIV感染者は「免疫不全者」ではない
・良好にコントロールされているHIV感染者が他者へHIVを感染させるリスクは非常に小さい
・不用意な治療中断は時に重大な結果をもたらす
・一部の抗HIV薬は高度の薬物相互作用を有する
・針刺し事故時に予防内服が有効である
・事故後の服薬開始はできるだけ早い方が良い
・HIV感染症の専門家は決して相談を嫌がらない
(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓

