
臨床研修ブログ
- トップ
- 臨床研修ブログ
水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。
医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。
2年ぶり♪ 舩越先生のZoomレクチャー
先月のことになりますが、東京ベイ浦安市川医療センター救急集中治療科(救急外来部門)部長の舩越拓先生にZoomでレクチャーを行っていただきました。
ちなみに舩越先生は救急領域では名が知られた存在の先生で、多くの監訳や著書があり、レジデントノートなどの雑誌の企画も行っています。編集長とはIVRつながりで、兄弟子、弟弟子という関係です。コロナ前はリアルで、コロナ後はZoomでレクチャーをお願いしていましたが、大変お忙しい先生なので気づいたら前回から2年も経っていました。
今回の内容は「マイナーエマージェンシーの苦手意識を克服しよう」ということで、ERで遭遇するけど、その場限りの対応で終わらせてしまっていることの多い鼻出血を取り上げていただきました。しかも、鼻出血だけで1時間という濃い内容で、一緒に聞いていた編集長は非常に面白かったですね。
忙しい合間でスライドを300枚以上作ってくれたそうで、鼻出血以外のシリーズもあるそうです。今年は2~3か月おきに開催していただけるハズなので、次回以降も楽しみです。
(編集長)
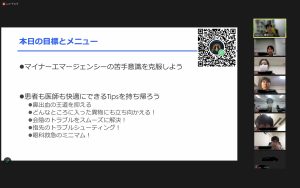
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆”レジナビFairオンライン2023 東日本”に参加します!
2月1日から開催されているレジナビFairに当院も参加します。
研修医も参加するので、どしどしご質問ください♪
当院は 2月21日(火)18:30からです。
レジナビのサイトからお申し込みが必要ですので、
下記リンクからお申し込みください。
↓
◆専門研修ブログもご覧ください!
当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。
↓
救命救急センターだより「頭部外傷とCT」
空を夢見る消化器内科医のNaoです。こんにちは。
皆さんは、放射線科の授業で「日本は世界でも非常に医療被曝の多い国である」という話をお聞きになられたことはあるでしょうか。日本は、世界で最もCTの設置台数が多いとされており、その影響もあって医療被曝が非常に多いといわれています。そのため自分では安易にCT撮影に頼らないように、と自制するように心がけています。
ところが先日、こんなことがありました。
救急外来に前期高齢者の転倒による後頭部打撲の患者さんが受診しました。担当してくれた研修医の先生からCT検査を行う方針の提案を受け、その根拠について尋ねました。打撲部は軽度の皮下血種と擦過傷はあるものの、神経学的異常はありませんでしたが、硬い地面に受け身なく頭部を直接打撲していることなどを踏まえて、CT検査を行いたいとのことでした。
研修医の先生は2年目ですので2か月後には単独で当直業務を行うようになります。自分であればCTは行わないだろうと考え、その意見は伝えましたが、一人の当直医として、自分で責任を取らなければならないとしたらどうするか考えてもらい、結果的にCTを行うこととしました。
結果的には、軽度の外傷性SAH、軽度の硬膜外血種、頭頂骨の骨折が認められました。自分の想定以上の所見でしたので大変驚きましたが、担当してくれた研修医は受傷起点から高リスクであるとちゃんと判断してくれていました。
頭部外傷時のCTの適応については成人と小児とで違いますが、成人ではカナダ頭部CTルール、ニューオーリンズ基準が有名かと思います。
【カナダ頭部CTルール】
- 受傷後2時間時点でGCS<15
- 65歳以上
- 2回以上の嘔吐
- 頭蓋骨開放あるいは陥没骨折疑い
- 頭蓋亭骨折疑い
- 受傷30分以上前の記憶の消失
- 危険な受傷起点
【ニューオーリンズ基準】
- 頭痛
- 嘔吐
- 60歳以上
- アルコールor薬物中毒
- 前向性健忘の持続
- 鎖骨よりも上部の明らかな外傷
- 痙攣
どちらの分類も一つでも当てはまればCTを推奨しています。安易に年齢で区切るのではなく、臨床判断も必要であると個人的には考えます。大事なのは、今回の研修医の先生のようにちゃんと患者さんの話を聞き、そこから判断する姿勢だなと、反省の当直になりました。
(Nao)

ERでの一コマ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆”レジナビFairオンライン2023 東日本”に参加します!
2月1日から開催されているレジナビFairに当院も参加します。
研修医も参加するので、どしどしご質問ください♪
当院は 2月21日(火)18:30からです。
レジナビのサイトからお申し込みが必要ですので、
下記リンクからお申し込みください。
↓
◆専門研修ブログもご覧ください!
当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。
↓
【周産期センター】産科緊急症例

初めてのB-lynch縫合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆”レジナビFairオンライン2023 東日本”に参加します!
2月1日から開催されているレジナビFairに当院も参加します。
研修医も参加するので、どしどしご質問ください♪
当院は 2月21日(火)18:30からです。
レジナビのサイトからお申し込みが必要ですので、
下記リンクからお申し込みください。
↓
◆専門研修ブログもご覧ください!
当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。
↓
大腿骨頭壊死症
ある日、ステロイドを含む化学療法で入院加療していた90代の患者さんに、「入院してから背中が痛いんですよ」と言われました。しかし診察すると、背中というよりは臀部の痛み。臀部だからまあ筋肉の痛みなのかな、と思い温湿布を処方しました。しかし、そのフォローの外来のカルテを確認してみると… 「大腿骨頭壊死 疑い」
あ。あ~~…と、鑑別に思いつきもしなかったことを反省しながら、改めて大腿骨頭壊死症について調べてみました。
◎大腿骨頭壊死症
・特発性大腿骨頭壊死症の男女比は1.2~2.1:1と男性に多い
・全国の有病率は10万人に18.2人
・Risk factorはステロイドの全身投与・飲酒・喫煙。そのほか、若年・男性・SLEを有することもrisk factorとして報告あり。
・ステロイドについては投与から1-3か月で起こることが多いとされる。
・壊死域は変化しないとされる
<診断基準>
X 線所見(股関節単純 X 線像の正面像および側面像で判断)
1.骨頭圧潰あるいは crescent sign(骨頭軟骨下骨折線像)
2.骨頭内の帯状硬化像の形成
1.2 については stage 4 を除いて(1)関節裂隙が狭小化していないこと ,(2)寛骨臼には異常所見がないこと,を要する.
検査所見
3.骨シンチグラム:骨頭の cold in hot 像
4.MRI:骨頭内帯状低信号域(T1 強調画像でのいずれかの断面で骨髄組織の正常信号域を分界する像)
5.骨生検標本での骨壊死像(連続した切片標本内に骨および骨髄組織の壊死が存在し,健常域との界面に
線維性組織や添加骨形成などの修復反応を認める像)
判定: 上記項目のうち,2 つ以上を満たせば確定診断とする.
除外診断: 腫瘍および腫瘍類似疾患,骨端異形成症は診断基準を満たすことがあるが,除外を要する.なお,外傷(大腿骨頚部骨折,外傷性股関節脱臼),大腿骨頭すべり症,骨盤部放射線照射,減圧症などに合併する大腿骨頭壊死,および小児に発生する Perthes 病は除外する.
・治療
免荷・物理療法/高圧酸素療法・ビスホスホネート製剤などの薬物療法は推奨度5(明確な推奨を提示しない)
骨切り術・人工股関節置換術は推奨度2(行うことを弱く推奨する)
(研修医S)

朝の回診で鑑別疾患を考え中
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆”レジナビFairオンライン2023 東日本”に参加します!
2月1日から開催されているレジナビFairに当院も参加します。
研修医も参加するので、どしどしご質問ください♪
当院は 2月21日(火)18:30からです。
レジナビのサイトからお申し込みが必要ですので、
下記リンクからお申し込みください。
↓
◆専門研修ブログもご覧ください!
当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。
↓
救命救急センターだより「低体温症」
週末救急医のNaoです、こんにちは。
(この記事は2023年1月末に書いてますが、公開されるのはちょっと先になるかと思います)
さて、日本列島には記録的大寒波が到来しており、当地域でも珍しく降雪しています。そうなると救急外来をにぎわすのが、事故や転倒そして転落などの外傷と低体温症です。
偶発的低体温症は、何らかの理由により体内の熱産生よりも放熱が上回ってしまい、深部体温が35℃以下になってしまった状態を指します。当院へ運ばれてくるような患者さんは、それに伴いCPAになってしまったような病態の方ばかりです。しかし、重度の低体温症に伴うCPAはROSCまでに比較的長時間を要しても神経学的予後が良好な例も報告されており、救急医としては本気で向かっていく病態です。特に深酒をして道路で寝込んじゃって重度の低体温になったような方は簡単には諦められません。
ちなみに、重度の低体温症からのCPAでは、ECMOを日常的に回している病院であれば、ECPRの良い適応になります。ECPRとは体外循環式心肺蘇生法で、救命センターに運び込まれたら直ちに静脈に脱血管、動脈に送血管を留置してV-A ECMOを回して呼吸循環動態を保つという方法になります。ECMOでは血液を加温することができますので、効率的な復温を図ることができるのです。
と、いつも通り前置きが非常に長くなってしまったのですが、今回は医学生や初期研修医の皆様がうっかり街中や雪山で低体温症の患者さんに遭遇してしまったときにどう対応したらいいか、という話を非常に簡潔にお話ししたいと思います。
寒い中に倒れている方がいたら、まずBLSのスタートです。が!
低体温症を疑う方の場合、呼吸、循環、意識の評価のほかに重要になるのが、震えの有無です。寒いのに震えが消失している場合は重度の低体温症を示唆するためです。震えているうちは、まだましです。
心肺停止に至っていない低体温症の場合、濡れている場合は衣服を除去して乾かします。そして、基本的には外から加温する必要がありますので、ホッカイロなどあれば使用しましょう。屋内や車内など暖房の効いた空間への収容も大切です。加温ができない場合は、衣類や毛布などで保温します。
いざというとき、医師として、医学生として動けるようにシミュレーションしておきましょう!何より、低体温に自分がならないように、泥酔して外で寝ちゃったりしないように注意してくださいね!
(Nao)

ICUでECMO抜去中
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆”レジナビFairオンライン2023 東日本”に参加します!
2月1日から開催されているレジナビFairに当院も参加します。
研修医も参加するので、どしどしご質問ください♪
当院は 2月21日(火)18:30からです。
レジナビのサイトからお申し込みが必要ですので、
下記リンクからお申し込みください。
↓
◆専門研修ブログもご覧ください!
当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。
↓
Fisher症候群・・・山中先生のZoomレクチャー
先月のことになりますが、今年度2回目となる山中克郎先生のZoomレクチャーを開催しました。
山中先生は、福島県立医大会津医療センター総合内科の教授として活躍されていますが、総合内科の大御所の一人です。著書もたくさんあります。
コロナ前は当院にお越しいただいていましたが、コロナになってからは年に2回のペースでZoomでのレクチャーをお願いしています。今年度は昨年5月に開催しましたが、それに続いてのレクチャーとなりました。
今回は神経内科領域の話題でした。その中から1つシェアしたいと思います。
40歳代男性が「ふらつき」と「話しにくい」を主訴に受診。病歴では2週間前に友人と焼肉を食べて、その後発熱と水様性の下痢を来しました。3日前からふらつきと話しにくさ、むせこむようになりました。受診時は複視の訴えもありました。身体所見では左右の眼球運動が悪く、嚥下障害と構音障害を認めました。膝踵試験は両側で稚拙。さらに上腕二頭筋、上腕三頭筋、膝蓋腱、アキレス腱反射は消失していました。さて、疾患は?? (ちなみにJ1の研修医S先生は見事に診断していました♪)
↓
↓
急性の外眼筋麻痺、運動失調、腱反射消失があり、さらに抗GQ1b IgG抗体>3.00 陽性が判明し、Fisher症候群と診断されました。
Fisher症候群
• ①急性の外眼筋⿇痺、②運動失調、③腱反射消失
• 瞳孔異常、眼瞼下垂、顔⾯神経⿇痺、球⿇痺、四肢の痺れ
• 先⾏感染(インフルエンザ桿菌、カンピロバクター)後に発症。1~2週間の進⾏後に⾃然軽快
• ギランバレー症候群の亜型
• ⾎清ガングリオシドGQ1b IgG抗体陽性(80-90%)
• 動眼、滑⾞、外転神経はGQ1bが豊富
• 男︓⼥=2︓1 平均発症年齢40歳
• 意識障害などを起こしBickerstaff型脳幹脳炎に移⾏することあり
さらに、今回の契機となったのは焼肉(たぶん生焼けの肉)からのカンピロバクター感染ですが、これについてもまとめていただきました。
カンピロバクター感染症
症 状)・⽔様性下痢(しばし⾎便)
・臍周囲の腹痛
・嘔気/嘔吐
・前駆症状︓発熱、悪寒、頭痛、倦怠感
その他)・潜伏期︓2-7⽇
・最も多い⾷中毒
・5-6⽉、9-10⽉に多い
・鶏⾁の>50%は感染
・⼗分加熱されていない鶏⾁は危ない
・ギラン・バレー症候群と関連あり
(編集長)
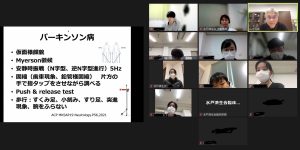
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆”レジナビFairオンライン2023 東日本”に参加します!
2月1日から開催されているレジナビFairに当院も参加します。
研修医も参加するので、どしどしご質問ください♪
当院は 2月21日(火)18:30からです。
レジナビのサイトからお申し込みが必要ですので、
下記リンクからお申し込みください。
↓
◆専門研修ブログもご覧ください!
当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。
↓
感染性心内膜炎の手術適応
前回は感染性心内膜炎(IE)の症例を紹介しました。IEは抗生剤加療で軽快するケースもありますが、中にはすぐに手術に踏み切らないといけないものもあります。今回はIEの外科的治療についてまとめました。
外科的治療は、進行する心不全,心内構築の破壊,難治性感染症,塞栓症の可能性の際に考慮するものですが、起炎菌や併存疾患などによっても影響を受けるため、そのタイミングなどは症例ごとにチームで検討を要します。中でも早期の手術を考えなくてはいけないケースは以下の通りです。
・うっ血性心不全
IEで最も多くみられる合併症であり、弁破壊による逆流が原因となり発症します。NYHA分類Ⅲ-Ⅳ度であればそれ単独で緊急手術の適応であり、Ⅱ度であっても重度の弁逆流を伴う場合には肺高血圧等認めた際に早期手術の適応となります。
・抵抗性感染
最も効果的な抗菌薬が一定期間(3-5日程度)適切に投与された後も、血培が陰転化せず、発熱・白血球上昇・CRP高値などの感染所見が持続する場合には、治療抵抗性感染と判断し早期に手術を行う必要があります。また、抗生剤加療が奏功しにくい真菌・グラム陰性菌・MRSAなどの多剤耐性菌は治療抵抗性の経過をとることが多く、手術適応となります。
・疣腫が巨大な場合
重度の弁機能障害を伴う10mm以上の疣腫を有する自己弁IE患者に対しては、できるだけ早い手術を推奨する、とされています。
前回の記事で紹介した症例では、幸い塞栓症等の発症はなく疣贅も抗生剤投与後数日のうちに消失しましたが、僧帽弁腱索が断裂しておりsevere MRを認めました。心不全の予防の観点から、外来フォローののち待機的に手術の方針となりました。
参考資料:感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン(2017年改訂版)
(研修医S)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
https://recruit-mito-saisei.jp/entry
◆専門研修ブログもご覧ください!
当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。
↓
救命救急センターだより「医療とお金」
皆さんこんにちは。空飛ぶ消化器内科医をめざすNaoです。
突然ですが、皆さん、命とお金どちらが大切でしょうか?命は金に換えられない。かけがえのないものだ。本気でそう思いますか?
僕は昔ブラックジャックを好きでずっと読んでいましたが、ブラックジャック先生は、この質問をずっと患者に投げかけ続けていました。金のあるものはいとわずブラックジャック先生の最高の医療を享受でき、金のないものは苦労して金を工面してブラックジャック先生の医療を受ける。資本主義の最たるものなのかもしれません。
さて救命センターで使用する薬剤には非常に高額なものがあります。例えば抗凝固薬の拮抗薬であるイダルシズマブやヒトプロトロンビン複合製剤などはそれぞれ1回あたりの薬剤コストが20万や15万ほどかかります。抗DIC薬のトロンボモジュリンアルファは1日当たり8万程度のものを数日間投与します。
抗がん剤治療に目を向けますと、ニボルマブという薬剤は発売当初の話ですが、1年あたりの一人の薬剤費が3500万円に上るといわれていました(現在は薬価改定されています、依然として高価ですが)。
私たちの使用する薬剤のコストは医療費という形で、みんなで背負っているわけですが、これがもし、日本の皆保険制度が破綻し、全て自費診療となった場合に、それでもなお、お金より命が大切だと言えますか。
コロナで人工呼吸器からECMO, CHDFとなった場合に、1日当たり10万円以上のお金をかけて延命していくわけですが、1日10万円のお金を全額自分で払うとなった場合にも、お金より命が大切だと言えますか。
実際に医師として働く中では、こっちの薬よりこっちのほうが効果は強いけど、でも効果のわりに薬価は倍違うし…など色々な小さなことを天秤にかけながら医療を推し進めていくことになります。それでも、日本の医者はまだいいほうですね。みんな保険に入っていますから、自費診療の患者さんの懐具合を心配する必要は殆どの場合ありません。
救命センターにはいろいろな事情で医療に近づけなかった人が、消えかけの灯状態で搬送されてくることが多々あります。でも、救急外来では、目の前の消えゆく灯を保ち続けるために、とにかく全力を尽くし続けます。そこに打算はありません。こんな医療を行ったら費用が、この薬剤を投与したら費用が、などと細かいことを天秤にかけて検討している間に灯が消えてしまうのです。ですから目の前の患者さんにとにかく全力を尽くします。
なので、あとで「あちゃーっ」となることもないわけではないのですが、それも含めて救命センターは楽しいところです。
ちなみに当院は済生会の一員でありますので、命は金に換えられない、かけがいのないもので、それに最も近い医療ができる場所であると思います。当院は、医療者としての技術だけでなく、心も育てられる、そんな研修病院であると思っています。
(Nao)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
https://recruit-mito-saisei.jp/entry
◆専門研修ブログもご覧ください!
当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。
↓
合格祈願2023
医師国家試験も、いよいよ今週末となりました。
3年前からのコロナ流行で、大学での実習も大きく影響を受けましたが、そのような中であなたは幾多の試験を乗り越えて、コツコツと勉強を続けてきた訳ですから、必ずや合格できます。
先日は当院の内定者向けにZoomで激励会を開催しました。勉強の邪魔をしないように、ごく短い時間でしたが、先輩となるJ1から激励のアドバイスがありました。少しでも役に立ってもらえたと思います。
もちろん試験では何が起こるか分かりませんので、あと少し、最後まで気を抜かずに頑張ってください!
あなたも合格を手にして、春から臨床の現場で一緒に人のために役立つ仕事をしましょう!当院スタッフ一同、あなたの合格を心よりお祈り申し上げます。
(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
https://recruit-mito-saisei.jp/entry
◆専門研修ブログもご覧ください!
当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。
↓
基本的臨床能力評価試験2023
毎年この時期になると基本的臨床能力評価試験(GM-ITE)というものがあります。日本医療教育プログラム推進機構(JAMEP)というNPOが行っている研修医向けのテストです。
研修医の客観的な臨床能力の実力を知ることができ、研修指導や臨床研修プログラムの評価・改善にも使えるというのがウリです。はじめのうちは受験する病院は少なかったのですが、近年では多くの病院で受験するようになっているようです。
編集長も経験がありますが、初期研修中はホントに自分は実力がついているのか?と不安になることがあります。自分の実力を知る方法としては、他の研修病院に行った同期の研修医と会話する時くらいで「奴はスゲーな!」とか、「自分は結構できてるかも」と勝手に判断するくらいしかありませんでした。でも、このテストを受ければ自分の実力が全国でどのあたりなのかが分かるので、とても良い機会だと思っています。
毎年当院のマッチング研修医には受けてもらっていますが、先日全員の試験が終わりました。昨年からCBT方式になったので、一応研修医室の自分の机で受験してもらいますが、他施設に研修に行っていたり、当直などで受験できなかった研修医は各自で受験となりました。
さて、試験の内容ですが、基本的臨床能力と言っても幅広い分野から出題され、総合診療をやっている病院には有利かもしれません。さらに英文の問題が去年より増えたようで、早く終わる人はおらず、全員が試験時間が終わるまで取り組んでいました。そうは言っても、臨床で経験したことをこまめに振り返っておけば、そこそこできる問題と思います。
例年当院の成績は偏差値50を超えていますが、今年の結果はどうでしょうか。楽しみです♪
(編集長)

テスト中の一コマ
(決してあきらめている訳ではありません)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?どんな生活を送っているのか?あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
https://recruit-mito-saisei.jp/entry
◆専門研修ブログもご覧ください!
当院には基幹型内科専門研修プログラムがありますが、その強みは消化器内科、循環器内科、腎臓内科の診療体制です。あなたも最短で内科専門医、そして施設を異動することなくサブスペシャルティ専門医と関連する各種の資格を取得できます。そんな内科専門研修プログラムを紹介するブログもぜひご覧ください。
↓

