
臨床研修ブログ
水戸済生会総合病院は、救急医療から緩和医療まで多彩な症例が経験できる総合力の高い地域の基幹病院です。
医師の生涯のうち最も実りある初期臨床研修期間を私たちは強力にサポートします。
服薬のアドヒアランス
編集長が外来をやっている時に重視しているのは、服薬のアドヒアランスです。
こちらとしては、患者さんの症状を軽減させたり、長期的な予後の改善やイベント抑制のためにお薬を処方している訳ですが、患者さんが服用してくれなければ、効果は期待できません。
服薬のアドヒアランスを確認する方法は、独自の技をお持ちの先生がいるので、是非聞きだして、参考にしてみると良いと思いますが、編集長は下記のようなところで確認しています。
その方法は、残薬の確認です。年に1,2回ですが、患者さんに「残薬を調整するので、次回の外来の時に自宅に残っているお薬をぜんぶ持ってきてください」と伝えています。
忘れる人もいますが、持ってきたらざっと数えて、残薬数が一定に処方を調整します。薬剤が多いと時間も取られて面倒ですが、どの薬剤が残っているのかを把握するだけでもOKです(もちろん処方のコメント欄に記入すれば、調剤薬局に依頼することもできます)。
この情報を把握すると、アドヒアランスを改善するための処方の変更に役立ちます。たとえば、朝夕に服用するDOACが、夕方の分だけ多く残っている時は、朝のみの服用のDOACに変更するなどです。
他にも、予想もしないような理由で服用していないことが明るみになることがあります。
ある時、血圧のコントロールがなかなか付かない高齢の患者さんに、残薬を持ってきてもらったところ、ナント降圧剤が380錠(!)も残っていたことがあります。詳細は忘れましたが、雑誌で読んだか、知人に言われたか、とにかく薬はあまり良くない旨のことを言われ、不安から服用しなくなったようです。
こんな時に、患者さんを責めてもいいことはありませんから、一度すべての処方をやめて、一剤ずつ、本人が納得するように時間をかけて再開していきました。編集長も、かなり凹んだエピソードなのですが、これ以降も年に数回は残薬確認するように患者さんに声掛けをしています。
ちなみに、ワーファリンを処方している患者さんは、ほぼ毎回INRをチェックしますが、これが安定している人はアドヒアランスの問題もほぼないというのが経験則です。
我々は、処方したから服用しているだろうと考えがちですが、患者さんは不安や不満を言い出せず、服用していないことは想像以上に多いようです。我々の方からいろいろな機会を作って、確認してみることが大事です。
(編集長)

お勉強中♪
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?
どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
https://recruit-mito-saisei.jp/entry
レッドマン症候群
今回はJ1のA先生が書いてくれた記事を掲載します。前回のさくらもち先生に続いてのブログデビューです。これも日常臨床での経験からの記事ですので、是非読んでみてください。
(編集長)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
こんにちは!
さくらもち先生に引き続きブログデビューさせていただきます、J1のAと申します。
文章を書くことが苦手なのでずっと逃げていましたが、そろそろ編集長に怒られそうなので書いてみます。拙い文章ですが、ぜひ読んでみてください^ ^
あなたが当直中に病棟から電話がかかってきました。
「入院している〇〇さんですが、顔面が紅潮し、体全体が真っ赤です!薬疹でしょうか!先生診てください!」
研修医になってまだ3ヶ月目。こんな電話かかってきたら、普通に焦ります。病棟に早足で向かいながらこの患者さんのことを思い出してみました。
「60歳台の男性でパーキンソン病でかかりつけの方で脱力、歩行困難で入院した方だな。熱があったから血液培養出したら、MRCNSが確か4本中3本から検出されて、抗菌薬始めてたな。」
そうこうしているうちに病室に着きました。
電話で聞いていた通り、患者さんの顔面は真っ赤に紅潮しており、四肢、体幹には紅斑が広がっていました。
バイタルは安定していて、患者さんの様子は落ち着いており、「痒くないし痛くもない」と言っています。ひとまず安心、、。
一体、この患者さんに何が起こっているのでしょうか?
↓
↓
そういえば、看護師さんからの電話の時、「薬疹かも」と言っていた気がします。
カルテでこの患者さんへの処方を確認してみました。
〜、〜、イーシードパール、セフトリアキソン、バンコマイシン
ここまで読んで分かったあなたはもう国試合格間違いなしです。おめでとうございます。今すぐ勉強をやめて遊びにでも出かけてください。
では、答え合わせです。
“レッドマン症候群”という名前を聞いたことがあるでしょうか?
レッドマン症候群とは、バンコマイシンの急速投与によりヒスタミンが遊離されて生じるアナフィラキシー様反応で、顔面、頸部、体幹、四肢に搔痒感と紅斑性発疹が現れます。ほかには、脱力感、血管浮腫、胸痛・背部痛なども起こり得ます。発症機序にIgEは介在しないためアレルギー反応ではありません。
ここでバンコマイシンについて簡単におさらいです。
バンコマイシンはグリコペプチド系の抗菌薬で細胞壁の合成を阻害します。MRSAを含めたグラム陽性菌にのみ有効です。基本は点滴投与ですが、偽膜性腸炎には経口投与でしたよね。
忘れてはならないのは、薬物血中濃度モニタリング(TDM)が必要ということです!(国試頻出です‼️)
濃度が高ければ腎障害などの重篤な副作用を引き起こしますし、低い状態が続けば耐性菌が生えてしまうという、なかなか難しい抗菌薬です。
バンコマイシンの初回TDMは、投与3〜4日目(投与4〜5回目)に行うことが望ましいとされています。採血の時間帯ですが、「トラフ」と呼ばれる投与直前(約30分前)に行います。(なぜこのタイミングかを説明すると長くなってしまうのでぜひ調べてみてください。) また、場合によっては「ピーク」と呼ばれる点滴終了後1〜2時間のタイミングで濃度を測ることもあります。
さて、レッドマン症候群の話に戻りましょう。
レッドマン症候群を引き起こさないためには、バンコマイシンの点滴を60分以上かけてゆっくり点滴静注することがとても重要です。
実際に、上級医がオーダーしたカルテを見てみると、「投与時間1時間30分」としっかり書いてありました。
もし、あなたがバンコマイシン投与中の患者の全身の紅斑をみたら、すぐにアレルギーと判断するのではなくレッドマン症候群を疑って投与速度の確認を行いましょう!
レッドマン症候群は抗ヒスタミン薬により改善させることができます。この患者さんは、ポララミンを投与したところ翌日には紅斑は消退していました。
ここまで読んでいただきありがとうございました。バンコマイシンについて少しだけ詳しくなっていただけたかなと思います。
また、ぜひこのブログに遊びに来てください!
見学もお待ちしております\(^^)/
(A)

ERでの一コマ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?
どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
https://recruit-mito-saisei.jp/entry
抗てんかん薬に潜む落とし穴
今回はJ1のさくらもち先生が書いてくれた記事を掲載します。今回がブログデビューですが、日常臨床での気づきをまとめてくれています。そしてさくらもち先生のキャラが出ている文章ですので(笑)、是非読んでみてください。
(編集長)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
こんにちは。さくらもちです。
私が先月経験した症例をご紹介します。意識障害で救急搬送された施設入所中の高齢女性。バイタルは安定していました。
さて、意識障害の原因を考えます。鑑別はたくさん挙がりますが、今回はこの方の内服薬に注目します。(AIUEO TIPSとか、このブログのどこかに記事が載っているはずですので、探してみて下さい♪)
内服薬→○○,○○,○○,炭酸リチウム,バルプロ酸ナトリウム
これを見たら、原因として挙げられることは何でしょう。
↓
↓
まず、てんかん発作が生じている可能性はありますね。この2剤は国試ではてんかん薬として勉強します。そして、さらに薬自体が引き起こす問題についても考えていきます。
まず、炭酸リチウム
すぐに思いつくのはリチウム中毒だと思います。特に腎臓が悪い人では注意ですよね。
これについて詳しくは、このブログの記事にあったので割愛します。ぜひ読んでみてください。
次!(今回はこれが言いたかった)
バルプロ酸ナトリウム
↓
↓
↓
アンモニアも測りましょう!
(全然知らなかったですよね〜 わかる〜〜)
そもそもバルプロ酸Naは、脳内のGABAやドパミン濃度を上げたり、セロトニン代謝を促進したりするお薬です。これらの神経伝達物質たちが脳内の抑制系を賦活させる作用があり、だから抗てんかん薬として使われているわけですね。抗躁作用および片頭痛発作の発症抑制作用もあるそうです。抑える感じですね。
そしてこのバルプロ酸ナトリウム、代謝の過程に注目しましょう。
尿素サイクルって覚えているでしょうか。国試でもなんとなく触れますよね。バルプロ酸ナトリウムの代謝過程で、尿素サイクルの働きが阻害されるために、アンモニアの分解が進まなくなり、蓄積してしまうわけです。(カルバミルリン酸合成酵素Ⅰ(CPS-Ⅰ)の活性が阻害され、カルニチンも減り、β酸化が抑制され、、、、など、色々詳しい機序が気になる方は調べてみてください)
このようにして、バルプロ酸ナトリウム内服中の方の身体の中では、高アンモニア血症が生じる可能性があります。
バルプロ酸ナトリウムの服用開始から高アンモニア血症が発見されるまでの期間は,急性中毒を除けば数ヵ月から10 年以上で、またその症候も昏睡や意識障害から無症状の例まであり、その期間や症候は症例により大きく異なると報告されています。ずっと服用しているから大丈夫と言えないし、症状も分かりにくそうってことですね。
ちなみに他の抗てんかん薬と併用することで、高アンモニア血症のリスクが高まるそうです。また、発熱時、嘔吐、下痢を伴う流行性疾患を伴った場合も高アンモニア血症をおこしやすいので、注意しましょう。
長くなりましたが要は
「長期にバルプロ酸ナトリウムを飲んでいる人では高アンモニア血症の可能性がある」
このことだけ頭の片隅に入れておいてもらえたらおっけーです。
症例に基づいた話に戻ると、
意識障害の患者で抗てんかん薬飲んでいる方
↓
リチウム中毒、高アンモニア血症もチェックしましょう! いずれも血中濃度の測定が大事です。
ただし!最後に1つだけ!
アンモニア濃度測定には忘れてはいけないポイントが! 国試にもでます!
↓
↓
検体を放置すると偽性にアンモニアが高値になってしまうこと、ですね
放っておくと赤血球中のアンモニアが遊離などしてしまうせいです。なので、研修医がアンモニア測定のオーダーをだしたら、自分で採血して自分で検査室まで持っていきましょう。(上級医がオーダーした場合も研修医が率先して持っていくと良い運動になりますよね)
以上大変長く読みづらい文章になってしまいましてすみません、、
これでも書くのに2ヶ月かかってしまいました。文章って難しいですね。
(さくらもち)
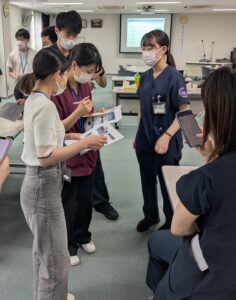
水戸医学生セミナーでの一コマ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?
どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
https://recruit-mito-saisei.jp/entry
突然の背部痛
あなたがER当直をしていたら、早朝にホットラインが鳴りました。60歳台の男性が就寝中に突然の左背部痛を自覚し、改善がないことから救急要請したようです。
ERに搬送されてきましたが、バイタルは微熱はあるものの血圧等は安定していて、あまり重篤感はありません。左背部痛は持続していましたが、体動で増強するそうです。
あなたは何を鑑別に挙げますか?
↓
↓
体動で増強する胸痛では、胸膜炎も鑑別に挙げてください。もちろんERでは重篤な疾患を除外することが大事ですので、大動脈解離やSTEMIを念頭に心電図や造影CTは考慮すべきですが、痛みの性状を把握することで鑑別がかなり絞り込めます。この症例では、診察の時に深呼吸をしてもらったところ左背部痛の増強がありました。
CTは大動脈解離の所見はなく、下図のように左背側の胸膜に接した肺炎像で、血液培養や喀痰培養は陰性でした。しかし臨床症状と尿中抗原陽性であったことから肺炎球菌性肺炎からの胸膜炎と診断しました。抗菌薬(CTRX)の投与で、胸膜炎の悪化もなく速やかに改善が得られました。

ここで肺炎球菌性肺炎の特徴について少しまとめておきます。
・肺炎球菌は引き起こす炎症反応が非常に強く、患者さんもぐったりしていることが多い。
・抗菌薬治療によって肺炎球菌自体は死滅していても、引き起こされた炎症反応が長引くことがある。
・このため、治療にも関わらず体温や採血データ(WBC,CRP)、胸部レントゲンがすぐに改善しないことがしばしばみられる。
・ただし、ぐったりしていた患者の自覚症状は改善してくるので、安易に抗菌薬の変更を行わない。
・市中肺炎の中では胸膜炎を合併する頻度が最も高い。
・古典的症状として突然の発症、膿性痰、胸痛などがあるが、あくまで非特異的。特に高齢者では非典型的な症状を呈する。
・市中肺炎の中では、肺炎球菌が最も血液培養が陽性になりやすいと言われ、陽性率は15~25%。
・菌血症を伴う肺炎球菌性肺炎の死亡率は2倍とされており、重症度把握や予後予測のために血液培養の採取は重要。
今回の症例は胸膜炎を合併した市中肺炎で、当初から起炎菌として肺炎球菌を疑っていましたが、尿中抗原から診断に至った症例です。肺炎球菌性肺炎では胸膜炎を合併しやすいことは、ぜひ覚えておいてください。
(参考:レジデントのための感染症診療マニュアル 第4版)
(編集長)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?
どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
https://recruit-mito-saisei.jp/entry
挿管中は“DOPE”を確認
80歳台の男性が肺炎で入院しました。もともと肺気腫があって加療されていた方です。酸素と抗菌薬を開始して、気管支拡張薬の吸入とステロイドの全身投与も行いましたが、酸素化が悪くて気管内挿管をして人工呼吸器管理になってしまいました。
その数日後の夜にあなたが当直をしていたら、病棟から「○○さんのサチュレーションが下がっています!」とコールがありました。患者さんのところに向かいながら、何をすればいいのか考えてみたのですが、あなたならどうしますか?
↓
↓
人工呼吸器の有無に関わらず、病棟からサチュレーションの低下でコールされることが日常的に良くあります。たいていの場合は看護師さんは痰の吸引などをやったうえで、改善がない時にコールしてくれるので、他にチェックすることを確認しておくことは有用です。こんな時に役に立つのが「DOPE」です。
DOPEとは
D(Displacement):
気管チューブの位置異常を確認します。抜けていないか、深すぎないか、必要なら胸部レントゲンで確認をします。
O(Obstruction):
気道の閉塞がないかを確認します。喀痰によるものが多いと思いますが、チューブの折れ曲がり(キンク)も確認します。喀痰が多い時は気管支鏡での吸引を行うこともあります。
P(Penumothorax):
陽圧換気による気胸は常に考えておく必要があります。胸部レントゲンだけでなく、経時的に皮下気腫が出現していないかの確認も行います。
E(Equipment failure):
チューブの接続不良や接続間違い、設定間違いがないかといった機器の不具合がないかを確認します。よく分からなければ臨床工学技師さんを呼んでみてもらいましょう。
人工呼吸器に苦手意識があっても、これらの対応はあなたでもできます。ぜひ覚えておきましょう。
ちなみにこの患者さんは、かなり喀痰量が多かったので、体位をかえて、頻回の吸引でサチュレーションが改善してくれました。体位ドレナージは思っている以上に有効なことがありますので、ぜひ試してみてください。
(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?
どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
https://recruit-mito-saisei.jp/entry
PSA(前立腺特異抗原)が高値でした!
70歳台の男性が発熱を主訴に入院しました。エコーで前立腺肥大と多量の残尿を認め、尿所見と合わせて尿路感染症と診断しました。尿道カテーテルを挿入して抗菌薬の点滴を開始し、さらにあなたは前立腺がんの合併があるかもしれないと思って、採血の際にPSA(前立腺特異抗原)も追加しました。順調に解熱が得られたのですが、数日後に戻ってきたPSAの結果を見ると、ナント38ng/mlと今まであなたが見た中で一番の高値でした。
慌てて泌尿器科の先生のところに「PSAが高値でした!」と相談に行ったのですが、「どうせ○○〇だから、あてにならないよ」と言われて終了でした。いったに何があったのでしょうか?
↓
↓
PSAは前立腺がんの際に上昇する腫瘍マーカーですが、ご存じの通り前立腺肥大でも上昇します。でも、実はこれ以外に下記のような状況でもPSAが上昇することが知られています。
・前立腺炎:急性・慢性を問わず、炎症があるとPSAが高くなることがあります。
・尿路感染症:感染が前立腺に波及すると、これも一時的な上昇要因になります。
このほかにも
・尿道カテーテルの挿入や膀胱鏡検査
・自転車やバイクの長時間運転
・射精や前立腺マッサージ
・放射線治療後に一時的にPSAが上昇するバウンス現象(再発と区別が難しくなる)
つまり、PSA値の変動は必ずしも「がんの進行」ではなく、一時的な刺激や良性の変化によることも多いため、1回の数値だけで判断せず、経過観察や追加検査が重要になります。
冒頭の症例は、尿路感染症や尿道カテーテル挿入といったことが影響してPSAが高値になったと考えられます。尿路感染症がしっかり落ち着いてから、もう一度測定してみるのが大事になります。
(編集長)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?
どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
https://recruit-mito-saisei.jp/entry
SGLT2阻害薬の落とし穴(その4)
そろそろ⻑くなって来ましたので治療について、ざっと整理して今回の投稿を終わりたいと思います。
euDKAの治療も⼀般的なDKA治療に準じます。
・DKAと診断されれば、SGLT2阻害薬を即座に中⽌すること
・prehospitalでの治療⽅法として推奨されるプロトコールは以下の2つ
STOP diabetic ketoacidosis protocol
STICH protocol
STOP-DKAプロトコルはカナダで使われているもの、STICHプロトコルは⽶国で使われているものです。興味を持った⽅はご⼀読ください。「SGLT2阻害薬の使⽤を中⽌して、炭⽔化物とりながらインスリン投与量を増やせ」というプロトコール。
病院に来ていただくのが前提条件ですが…。
・inhospitalではガイドライン通り治療する。
等張液輸液、電解質補正、アシドーシス補正、インスリン投与が主な治療
⾼⾎糖は6時間、ケトアシドーシスは12時間以内の補正を⽬指す
⾎糖値200mg/dL以下になったらケトアシドーシス補正継続と低⾎糖予防のために糖を負荷する。
※ケトアシドーシスが改善されるまではインスリン静注をやめない
・euDKAではそもそも⾎糖値が⾼くないので、治療初期から糖含有液を使⽤するところが、普段の⾼⾎糖を伴うDKAへの治療と異なる。⾎糖値は150-250mg/dLで保持(Diabetes Care 2009;32:1164-1169.)
<まとめ>
・SGLT2阻害薬は⽐較的新しい糖尿病治療薬だが、特に1型糖尿病やリスク因⼦を持つ患者ではDKAのリスクが増⼤する
・その場合、euglycarmic ketoacidosisと呼ばれる⾎糖値が 基準値内〜軽度上昇程度にとどまるケトアシドーシスを呈することがあり、診断の遅れにつながる恐れがある
・呼吸の評価は呼吸様式まで観察する
・SGLT2阻害薬内服している患者で、ケトアシドーシスの症状や増悪因⼦を持つ場合には患者のケトンをチェックする
・尿中ケトン陰性の場合でもDKAを疑うなら⾎中ケトン濃度を測定することを躊躇わない
・治療はおおむねガイドライン準拠でよいが、より早い段階から糖含有液投与を要する
以上です。⻑い⽂章になってしまい申し訳ありませんでした。お付き合い頂きありがとうございました。
<参考>Musso G et al. Diabetic ketoacidosis with SGLT2 inhibitors. BMJ. 2020 Nov 12;371:m4147. PMID: 33184044
⽇本糖尿病学会編・著:糖尿病治療ガイド 2022-2023,p83,⽂光堂,2022
Goldenberg, R. M., Gilbert, J. D., Hramiak, I. M., Woo, V. C. & Zinman, B. SGLT inhibitors in type 1 diabetes: place in therapy and a risk mitigation strategy for preventing diabetic ketoacidosis ‐ the STOP DKA Protocol. Diabetes, Obes.Metab. dom.13811 (2019). doi:10.1111/dom.13811
(マッコイ)

これからPICC
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?
どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
https://recruit-mito-saisei.jp/entry
SGLT2阻害薬の落とし穴(その3)
今回も研修医のマッコイ先生の記事の続きです。
前回まではSGLT2阻害薬、DKA、euDKAについてシェアしてきましたが、今回はこれらを踏まえて、当初の疑問である「SGLT2阻害薬内服している⼈で意識障害を起こして救急搬送されたら何に気を付ける?」の答えとしてどこで疑って検査に進み、診断をつけたら良いかを考察したいと思います。
①PS(Primary Survey)での呼吸の評価
PSの段階可能であれば、それより前のInitial assessment での呼吸様式の異常でクスマウル⼤呼吸や頻呼吸など「深くて早い呼吸」でアンテナを⾼くすることが肝になりそうです。代謝性アシドーシスの存在を考えてDKAを鑑別にあげます。
呼吸の評価の奥の深さに様々な勉強会に出るたびに気付かされるのですが、回数だけでなく呼吸様式まできちんと評価してカルテ記載する。これは今後の臨床で必ず実施しようと思います。
②動脈⾎ガス評価
ここで注⽬するのは、まずはAGMAの有無かと思います。euDKAの存在を知った今だからこそ、⾎糖がそこまで⾼くないという理由で鑑別疾患から外さないことを⼼がけなければいけません。
③⾎清ケトン体の評価
代謝性アシドーシスを疑ったら、ガス+⾎清ケトンまでの評価で1セットここが今回の⼀番の学びのように感じます。ガス⾒ておしまいでは無い。肝に銘じました。
ちなみにもう⼀つポイントがありますが皆さん、お気づきでしょうか?それは検体の種類です。⾎清の検体でケトン体の⾎中濃度測定をする。これがポイントです。
<ケトンについて>
ケトン体とは、アセト酢酸、βヒドロキシ酪酸、アセトンを指します。3種類ありますが、尿検査ではβヒドロキシ酪酸を測定できません。DKAの時に上昇してくるケトン体はβヒドロキシ酪酸なので、尿検査だけだと⾒逃しが⽣じる可能性があります。
・通常の検査試験は、アセト酢酸>アセトンで感度良好であり、βヒドロキシ酪酸は検出できない。尿検査でケトン陰性は33%(6例/18例)
(Endocr Res. 2004 Aug; 30(3): 395-402.)
翻って考えると、尿検査でもしもケトン体陽性であれば診断に繋げてもよい。ポイントとなるのは、初療の段階では陰性となることがあるということ。
(Diabetes Care. 2009 Jul;32(7):1335-43.)
・重症DKAではβヒドロキシ酪酸:アセト酢酸=6:1 ⾎清βヒドロキシ酪酸でのDKA診断寄与 感度98%/特異度79%/陽性的中率34%(cutoff 1.5mmol/L)
(Diabetes Care. 2011 Apr; 34(4):852-4.)
つまり、ケトン⾎症を証明するのはβヒドロキシ酪酸がゴールドスタンダードということです。
(マッコイ)

ERでの一コマ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?
どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
https://recruit-mito-saisei.jp/entry
SGLT2阻害薬の落とし穴(その2)
今回も研修医のマッコイ先生の記事の続きです。
<DKAの主な所⾒>
・DKAの主な初期症状としては、悪⼼・嘔吐、⾷欲減退、腹痛、過度な⼝渇、倦怠感、呼吸困難、意識障害など
・⾝体所⾒では、Kussmaul⼤呼吸(過呼吸)、呼気のアセトン臭、⼝腔粘膜の乾燥、低⾎圧、頻脈などが主なものとなる
・アニオンギャップ開⼤性の代謝性アシドーシス(AGMA)
・⾎糖:250~1,000mg/dL
・⾎清総ケトン体≧3mmol/L
・HCO3≧18mEq/L
・pH≦7.3
以上が⼀般的なDKAの簡単な所⾒です。
次に、はぐれDKAとでも⾔いますか、euDKAについてまとめます。
<euDKA(WHO pharmacovigilance database)>
・上記の通り、DKAは典型的には⾼⾎糖があることが特徴ではあるが、SGLT2阻害薬内服中、妊娠中、⾷事摂取量低下(飢餓)、アルコール使⽤障害や肝硬変などでは1/3以上の割合で⾼⾎糖がない(<250mg/dL)が認められないことがある
・⾼⾎糖ではないことと、⾼⾎糖による浸透圧利尿が軽度であることから診断が遅れる可能性がある
・SGLT2阻害薬の観察研究によれば…1型糖尿病患者でのDKA発⽣頻度が相対的に⾼い
1型糖尿病…7.3 events/1000 patients-years
2型糖尿病…1.3-8.8 events/1000-years
・特に治療開始から最初の数か⽉でリスクが⾼くなる
・DKAイベントの76.8-85.2%が、SGLT2阻害薬開始から180⽇以内に発症している
・⾼⽤量の使⽤は低⽤量に⽐較して4.9倍リスクが⾼い
今回はここまで。
次回はこれらを踏まえて、当初の疑問である「SGLT2阻害薬内服している⼈で意識障害起こして救急搬送されたら何に気を付ける?」の答えとしてどこで疑って検査に進み、診断をつけたら良いかを考察したいと思います。
(マッコイ)

朝の慌ただしいEHCUの一コマ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?
どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
https://recruit-mito-saisei.jp/entry
SGLT2阻害薬の落とし穴(その1)
どうもはじめまして、研修医のマッコイです。
突然ですが、「無理なく痩せるならSGLT2ダイエット」なんて広告をあなたも⽬にしたことがあるのではないでしょうか? 今回は、昨今、糖尿病(DM)だけでなく慢性⼼不全や慢性腎臓病(CKD)に適応が広がっていたり、⾃由診療での適応外使⽤など様々な形で利⽤されているSGLT2阻害薬を服⽤されていた患者さんで意識障害があった時、どんなことを考えますか?そんな内容で記事を書かせて頂きます。
そもそもなぜ、この記事を書くことになったかと⾔いますと(余談ですがお付き合いください)…水戸済生会の研修医である私マッコイ(救急科志望)が総合内科をローテーション中にカンファレンスで指導医に問いかけられたことがきっかけでした。
指導医:「SGLT2阻害薬内服している⼈で意識障害起こして救急搬送されたら何に気を付ける?」
マッコイ:「えっとー…低⾎糖、尿路感染症とー…」
指導医:「ブログの記事書こうか^ ^」
はい、ということでこの度執筆の機会を預かる運びとなりました(笑)
この⼀年ローテーションしていて、当院の指導医の先⽣⽅に共通して本当にありがたいなと感じることなのですが、救急志望の僕なら例えばERでこうした背景のある患者さんが搬送された時にどんなことに注意するべきか、どんな検査を考慮しておくべきか、治療介⼊する上で気を付けることは、救急医のファーストタッチとアセスメント、専⾨科へのコンサルの仕⽅でどれだけ患者さんのその後の診療の質が変わるか、など、その先の進路を考慮した指導や問題提起をしてくださることです。指導医の親⼼のようなものに⽇々感謝しています。
さて、本題ですがSGLT2阻害薬内服中の患者で意識障害を起こしている場合に早めにルールアウトするべき疾患は糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)です。
しかも、この場合のDKAはeuDKA、euglycarmicなDKAだそうです。⾎糖値の上昇に乏しいDKA…FDAとEMAからも警告が出ています。症例報告を調べると稀なものってわけではなさそうです。
「は? じゃあ、そもそもどうやって初療で気付くんだ?」
「Primary survey(PS)やっている間に勘づくのは難しいそうだから、Secondarysurvey(SS)で内服薬の状況集めた時にやっと考慮することになるのかなぁ」
指導医や先輩医師の話を聞きながらそんな疑問を抱いたので、その部分も含めて書けたらと思います。
<SGLT2阻害薬とは何か?>
・⾎糖コントロール⽬的に、メトホルミン、SU剤、インスリンなどと併⽤され、第2-3選択薬として使⽤される
・2016年の英国では第2選択薬の14%、第3選択薬の27%を占めていた
・2019年の⽶国および欧州でのコンセンサスガイドラインでは、2型糖尿病かつ⼼臓⾎管疾患やCKDがある患者への使⽤がさらに推奨されている
・欧州や⽇本では、⾎糖コントロールを改善するためのインスリン補助役として承認されているGLT2阻害薬はほとんどない
・FDAは、1型糖尿病に対するSGLT2阻害薬使⽤はDKAのリスクが⾼いことから使⽤を推奨していない
・SGLT2阻害薬は膵島a細胞のSGLT2を阻害し、グルカゴン分泌を直接刺激。結果として内因性グルコース 産⽣・ケトン産⽣・脂肪酸の分解が促進される
・腎臓ではSGLT2阻害によりケトン再吸収を促進する
・腎臓の尿中からのブドウ糖排泄を促進することで⾎糖値を低下させる
・尿糖が増加し⾎糖値が下がることでインスリン分泌が減少
・インスリン:グルカゴン⽐が減少するため、肝臓でのケトン産⽣・遊離脂肪酸分解が阻害されなくなる
・尿糖による浸透圧利尿で脱⽔が誘発され、グルカゴン、コルチゾール、アドレナリンの分泌につながり、さらに脂肪酸分解とケトン産⽣が進⾏する
以上が、SGLT2阻害薬の特徴や薬効機序になります。
今回はここまで。次回に続きます。
(マッコイ)

ERでの一コマ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有するスペシャリスト
を目指します
◆病院見学に来ませんか?
当院の研修医がどんなふうに仕事しているのか?
どんな生活を送っているのか?
あなたの目で確かめてみてください!
病院見学をご希望の方は、下のフォームからご連絡ください。
なお、病院見学がむずかしい時は、Zoomで個別説明会を行っていますので、
下のフォームに「Zoom希望」と記入してご連絡ください。
↓
https://recruit-mito-saisei.jp/entry

