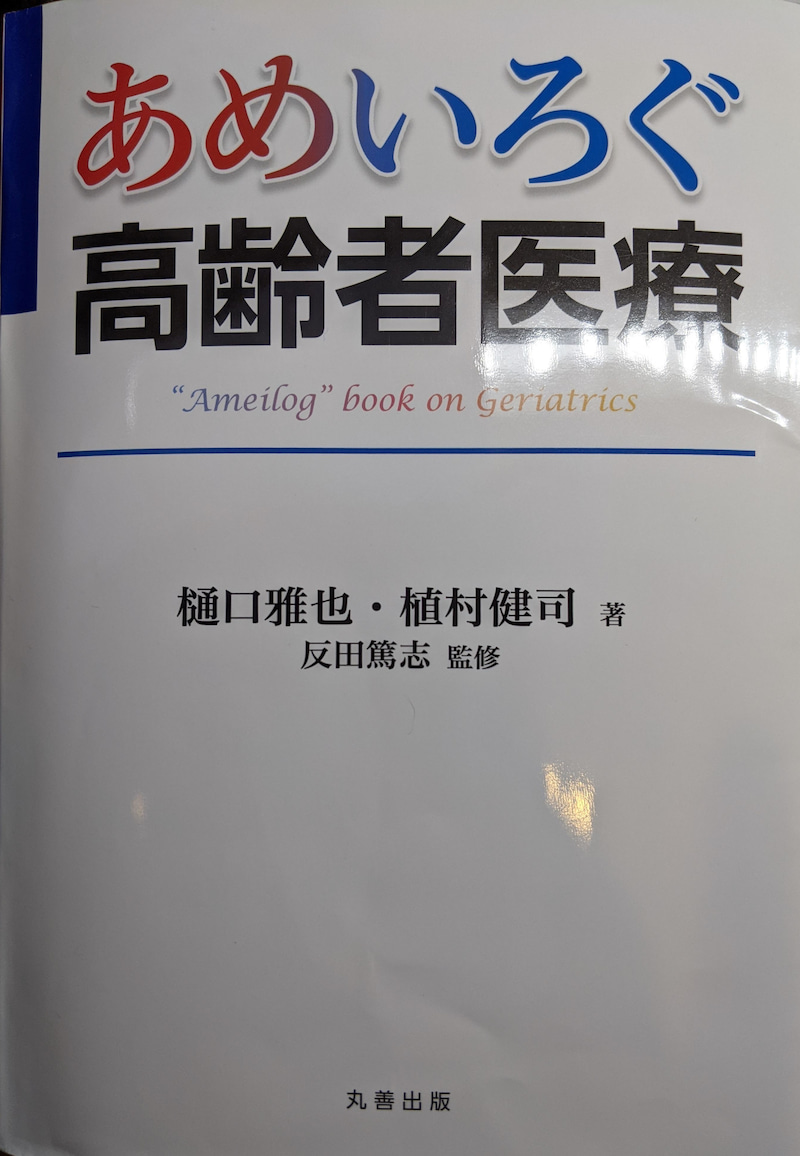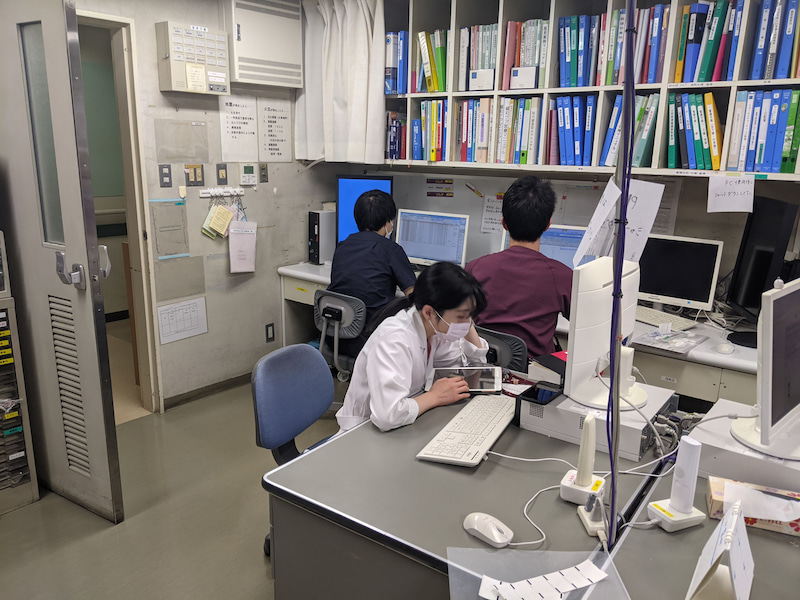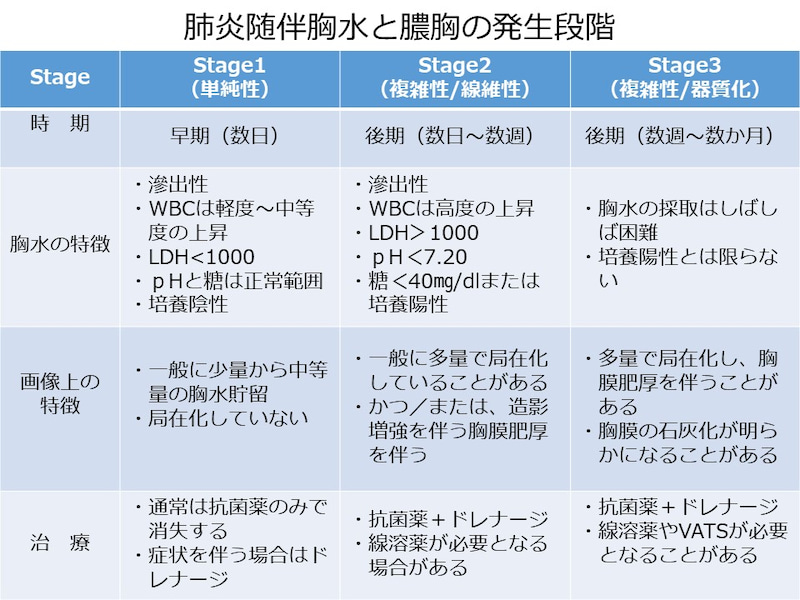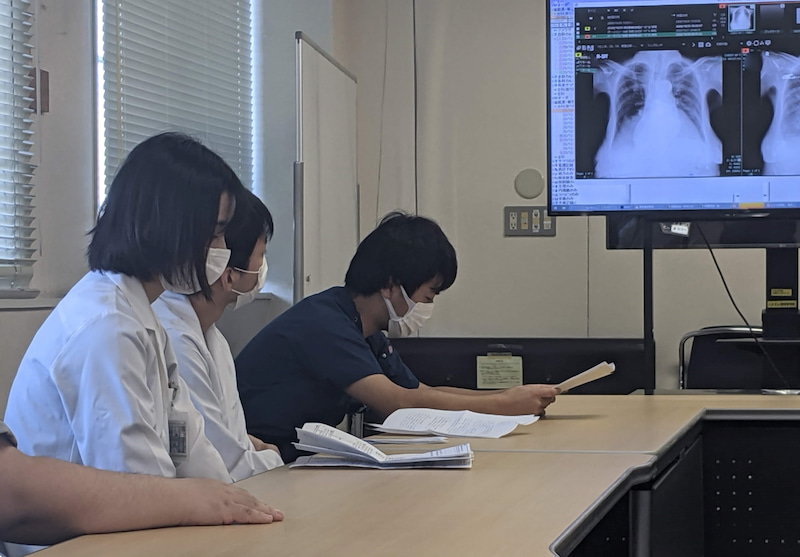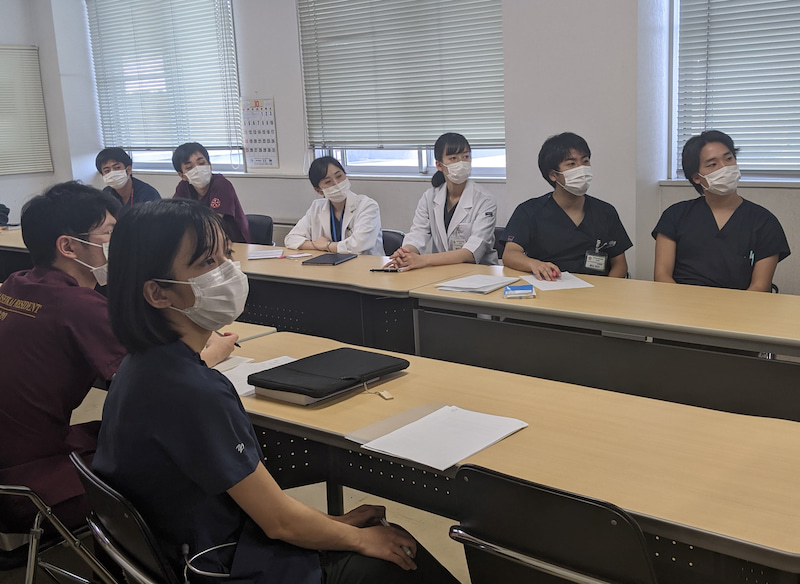前回まで栄養療法(主に経腸栄養)
について述べてきました。
早期に栄養療法を開始することで
予後を改善できますが、様々な
合併症に注意する必要があります。
チューブ閉塞、誤嚥/下痢等の
トラブルにはもちろん気をつけ
なくてはなりませんが、特に栄養療法
開始時に気をつけたい合併症に
Refeeding症候群があります。
Refeeding症候群とは:
[背景と病態]
長期に低栄養/飢餓状態にあった
人は、細胞内のミネラルが枯渇して
います。このような状態にある人に
対して急激に再栄養(Refeeding)を
行うと、インスリン分泌の増加により
グリコーゲンや脂肪、蛋白の代謝が
亢進し、P/K/Mg/Vit.B1などが大量に
浪費されてしまうほか、細胞内への
取り込みも促進され、急激に血中
濃度が下がってしまいます。
これにより代謝異常や致死的な
不整脈等、様々な全身合併症を
きたすことをRefeefing症候群と言います。
【臨床所見】
・低P血症(特に重要!)
→不整脈や血圧上昇/低下、
骨軟化症、白血球/血小板機能不全など
・低K、Ca、Mg血症
・Vit.B1欠乏
→Wernicke-Korsakoff症候群など
・うっ血性心不全
・末梢浮腫
【管理上の注意点】
◎ハイリスク患者に対しては慎重な
栄養計画とモニタリングが重要!
→5-10kcal/kg/day程度と通常の半分
以下で栄養を開始し、ゆっくり増やす
→症状等みながらP/K/Mg/Vit.B1の
補充を行なっていく
Q.どんな患者がハイリスクなのか?
A.神経性食思不振、慢性アル中、
糖尿病、担癌/術後、高齢者等
研修医が輸液や栄養の組成を
ゼロから考えていくのは非常に
難しく大変ですが、少しでも患者さんの
病態が良い方向へ向かわせられる
よう、しっかり勉強していきたいものです。
(Dr.K)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水戸済生会総合病院の臨床研修は
総合診断能力を有する
スペシャリスト
を目指します
◆レジナビFairオンライン
に参加します!
1月18日から開催される
初期研修医向けのWeb企画
レジナビFairオンライン2021
東日本Week
~専門研修(内科)プログラム~
に当院も参加します。
当院の出番は
1月20日(水)19時~
参加受付は当日15時までです!
ぜひご参加下さい!
◆新春企画!
Web版・個別病院説明会を
開催します。
そろそろ研修病院の情報を集め
始めないと。でも、Web情報だけで
いいんだろうか?
新型コロナの蔓延で、昨年以上に
病院見学がやりにくくなっています。
確かに病院見学に行く機会は減って
いますが、研修の実際を知ることは
できます!
昨年夏に開催して好評だったWeb版・
個別病院説明会を開催予定です。
開催期間
令和3年1月12日(火)
~1月29日(金)
*平日のみ対応
*時間はお申し込み後に調整します
所要時間
15~30分程度
*当院の初期研修医が直接
あなたの質問に対応します。
Zoomを使って直接当院の研修医
から、研修のホントのところを
聞き出してください!
↓
Zoomを使って直接当院の研修医
から、研修のホントのところを
聞き出してください!
◆こちらもご覧ください!
水戸済生会がレジナビ動画で
紹介されています!
「レジナビオンライン東日本」での
病院紹介動画がアップされています。
ぜひご覧ください。
特定看護師と朝の回診♪